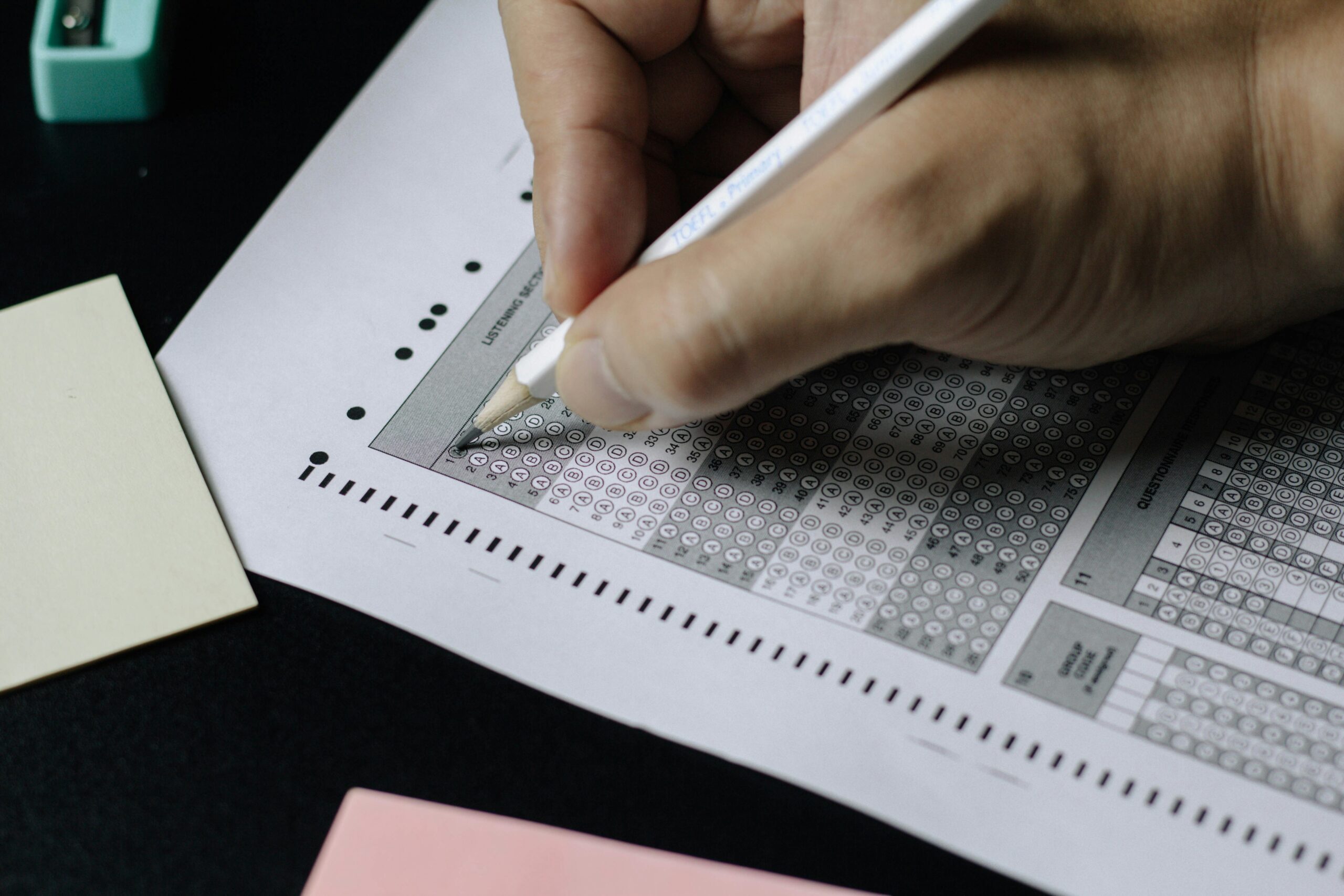【通関士試験対策】輸入通関のポイントを徹底解説!

通関士試験において、輸入通関の手続きは頻出の重要テーマです。実務でも不可欠な知識となるため、試験対策として正しく理解しておきましょう。本記事では、輸入申告の流れや関連条文を解説し、試験で問われやすいポイントを整理します。
輸入通関の基本
輸入申告の流れは以下の通りです。
- 輸入申告(税関への申告)
- 輸入許可(税関による審査・許可)
- 貨物の国内引取り
本記事では特に、輸入申告と輸入許可の手続きについて詳しく解説します。
輸入申告の特徴
- 申告価格: 課税価格は厳密に計算し、正確な金額で申告する必要があります。
- 申告単位: 財務大臣が定める単位(正味数量)で申告。
- インコタームズ: 申告価格はCIF(運賃・保険料込み価格)で統一される。
👉 関連用語: インコタームズとは?初心者向け解説
試験対策のポイント
通関士試験では、選択式や条文の穴埋め形式で出題されることが多く、正確な理解が求められます。
輸入申告の手続き
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
関税法第67条の2(輸出申告又は輸入申告の手続)
輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。
輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1. 前項の規定による承認を受けた場合
2. 当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、 税関長の承認を受けた場合
3. 特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合
試験対策ポイント
- 貨物の品名・数量・価格、その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。(輸出申告と同様)
- この部分は穴埋め問題で出題される可能性があるため、語句をしっかりと覚える。
- 基本的には保税地域に入れたあとに輸入許可がされますが、特例輸入者については例外がある。特例制度については、こちらの記事を参考👉。
https://tsukanboeki-shun.com/kouza-tokurei/
輸入申告に関する提出書類
関税法第68条
税関長は、輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
関税法施行令第61条
関税法第68条に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1. 便益を適用する場合 当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書(課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。以下この条において同じ。)の総額が二十万円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物に係るものを除く。)
…省略
3. 原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日においてその発行の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。
4. 締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書は、これらに係る貨物の輸入申告又は法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合又は当該貨物につき法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内)に、提出しなければならない。ただし、締約国品目証明書は、これに係る貨物の課税価格の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
試験対策ポイント
- 原産地証明書で便益を受ける場合必要な書類については、施行令第61条に規定されている。例外として、以下の内容については、書類の提出が省略できる貨物が挙げられている。
①課税価格の総額が20万円以下
②原産地が明らかな書類
③特例申告貨物
- 輸入申告の日において、その発行日から1年以上経過したものは無効。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は例外となる。
原産地虚偽貨物
関税法第71条
1. 原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
2. 税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
試験対策ポイント
- 原産地虚偽表示された貨物については、「消させ」「訂正させ」「積みもどさせ」る必要がある。
他法令の証明・確認
関税法第70条
1.他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
2.他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸出又は輸入の許可の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
3.第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。
試験対策ポイント
- 輸入する貨物が他の法律(食品衛生法、薬機法など)の規制対象である場合、該当する許可証や証明書の提出が必要。
輸入の許可前における貨物の引取り承認(BP承認)
関税法第73条
1. 外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
2. 輸入の許可を与えることができない場合においては、税関長は、輸入の許可前の引き取りの承認をしてはならない。
3. 輸入の許可前の引き取りの承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)、第五条(適用法令)、前条、第百五条(税関職員の権限)及び第百六条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。
試験対策ポイント
-
輸入申告後、輸入許可前に貨物を引き取るためには、関税相当額の担保を提供し、税関長の承認を得る必要がある。(絶対的担保)
郵便物の輸入申告
関税法第77条
1.関税を納付すべき物を内容とする郵便物があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。
2.日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
3.前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。
4.前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
ポイント
-
課税価格が20万円以下の郵便物は簡易な手続きで輸入申告が可能。
-
課税価格が20万円以上の場合は、簡易な手続きが不可となるが、寄贈物品については20万円を超えていても簡易手続きが適用される。
-
郵便物の関税の納付の手続きは、日本郵便株式会社に委託しなければならないとあり、
輸入者と税関の間に日本郵便株式会社が入るという構図となっている。
試験対策のポイント
条文の暗記
試験では、関税法や施行令の条文に基づいた問題が出題されることが多いため、条文の正確な理解と暗記が重要です。特に、関税法第67条や関税法施行令第61条などは頻出のため、特に力を入れておきましょう。
過去問を活用する
試験対策で最も効果的なのは、過去問を解くことです。
問題集については、こちらの記事も参考にしてください。👉
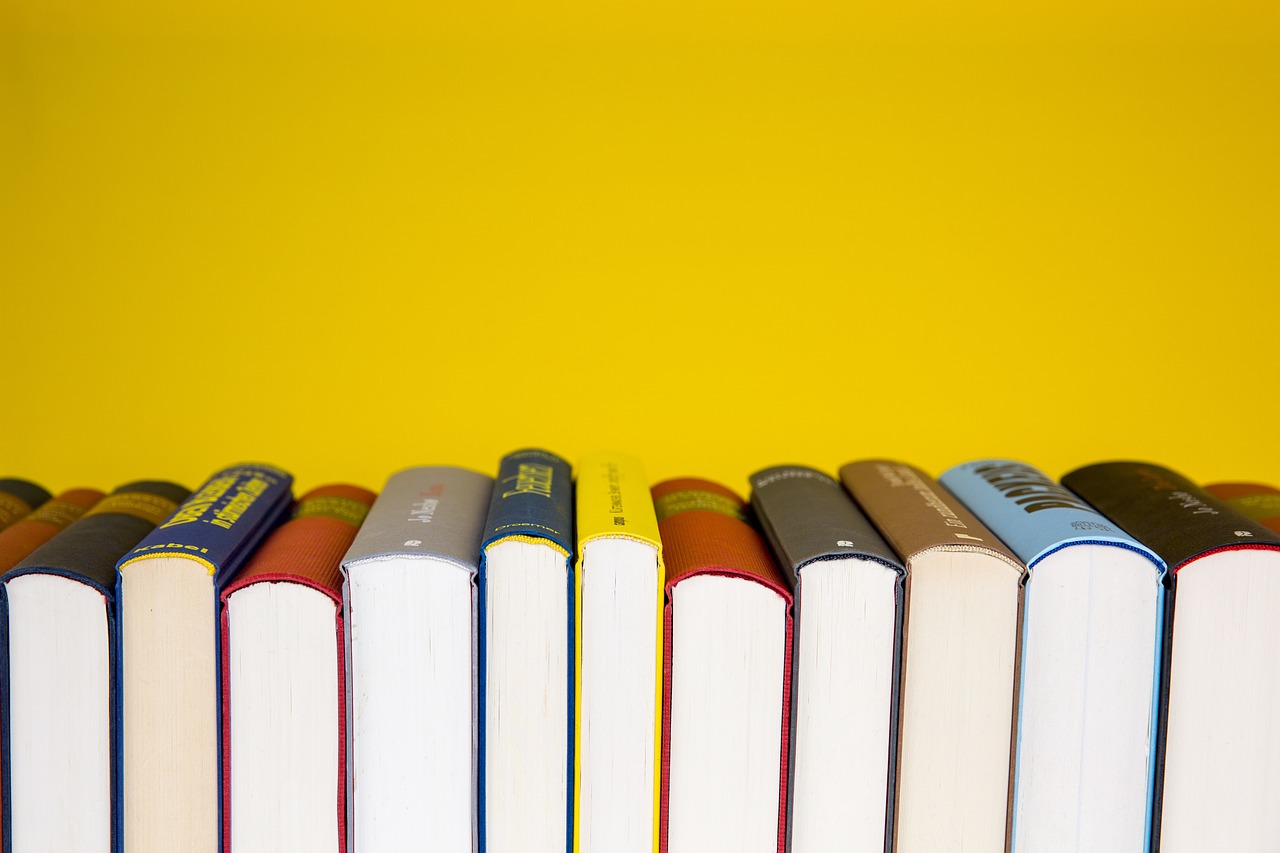
用語の意味を正確に理解する
輸入通関に関連する用語や定義(課税価格、インコタームズ、保税地域など)は試験で頻出です。これらの用語の意味や実務での取り扱いについて理解を深め、しっかりと記憶しておきましょう
こちらの記事も参考にしてください。👉

【通関士試験】過去問チャレンジ
まとめ
輸入通関の手続きは、関税法と施行令に基づいて規定されています。試験では条文の正確な理解が求められるため、過去問を活用しながら確実に押さえていきましょう。
次の講座を確認👉【保税地域・制度を詳しく解説!条文・過去問付き】

その他の講座はこちら👉