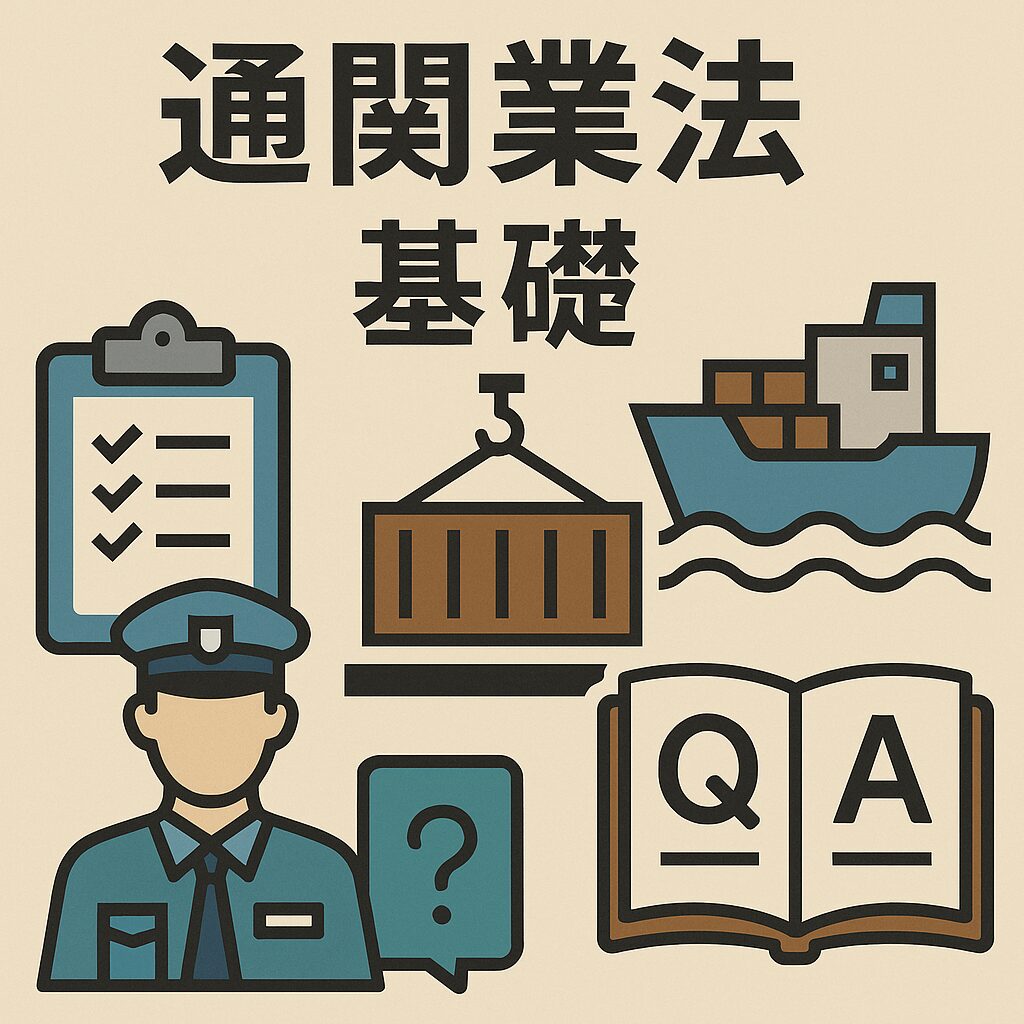通関士試験の通関業法のキホンをやさしく解説!

通関士試験では「関税法」「関税定率法」だけでなく、「通関業法」からも出題されます。中でも、定義や業務範囲、通関士の設置義務などの基本事項は頻出テーマです。
この記事では、通関業法の目的・通関業務・関連業務・帳簿保存などの条文ごとのポイントをわかりやすく整理し、試験対策に役立つ情報をお届けします。
通関業法とは?
通関業法は、通関業を営む者に関する法律で、業務の適正な運営を通じて関税申告や貨物の通関手続きを迅速かつ適正に実施することを目的としています。
【第1条】通関業法の目的
通関業法 第1条 目的
この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
📝試験対策ポイント
-
語群選択問題で問われやすい条文なので、文言を正確に押さえる
通関業務とは?【第2条】
通関業法 第2条 定義
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
イ、次掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又 は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続輸出(積戻しを含む。)又は輸入の申告
- 関税法第七条の二第一項の承認の申請
- 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
- 保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第五十六条第一項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第六十二条の三第一項の申告
- 関税法第六十七条の三第一項第一号の承認の申請
(2)関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
(3)通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく 税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述ロ、関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。
通関業法基本通達2-3
「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をも って通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいう。 この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の 業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。
【第2条】通関業務の定義
以下のような業務が含まれます:
1. 通関手続き
- 輸出(積み戻しも含む)・輸入の申告
- 特例輸入者の承認申請・特例申告
- 船用品積込みの承認
- 蔵入れ・移し入れ等のどこかに入れる搬入する承認申請
- 修正申告・更正の請求・納期限の延長修正 など
2. 通関手続き
- 行政不服審査法等に基づく、税関長・財務大臣への申し立て
3. 主張・陳述
- 通関手続等に関する主張、陳述
4. 書類の作成
- 各種申告書・申請書・不服申立書の作成(電磁的記録含む)
💡補足:通関業法基本通達2-3
無償であっても通関業務に該当。
📝試験対策ポイント
-
「通関業務=他人の依頼で行う」「独占業務である」点を明確に
-
輸出申告や更正請求、不服申立てなど具体的業務も選択肢に出やすい
関連業務とは?【第7条】
通関業法第7条(関連業務)
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
通関業法基本通達 7―1(関連業務の範囲等)
(関連業務)の適用については、次による。
- 通関業法第7条本文に規定する「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業 務」とは、法第2条第1号((定義))に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ、 事前教示照会
ロ、 不開港出入許可申請
ハ、 外国貨物仮陸揚届
ニ、 見本一時持出許可申請
ホ、 保税地域許可申請
ヘ、 外国貨物運送申告
ト、 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ、 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請
【第7条】関連業務の範囲
例えば以下の業務が含まれます:
-
事前教示の照会
-
不開港出入許可申請
-
外国貨物仮陸揚届
-
保税地域許可申請
-
輸出入差止申立への意見書提出
-
輸出入に必要な他法令の許可申請
📝試験対策ポイント
-
「通関業務に先行・後続・関連する業務」を整理しておく
-
毎年、通関業務と関連業務の区別問題が出題される傾向あり
-
すべて覚えるのが難しい人は「関連業務の具体例」から優先的に暗記を!
帳簿の記帳・届出・報告【第22条】
通関業法第23条(記帳、届出、報告等)
- 通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
- 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
【第22条】帳簿・届出・報告義務
-
帳簿記帳・書類保存
→ 関連業務も含めた業務内容・収入等を帳簿に記載し、3年間保存 -
従業者の届出
→ 通関士・担当役員の氏名と異動を財務大臣に届け出 -
業務報告の提出
→ 年1回、件数・料金などを記載した報告書を提出
📝試験対策ポイント
-
帳簿・書類は「閉鎖の日または作成日から3年」保存
まとめ:通関業法で押さえるべき試験ポイント!
| 条文 | 内容 | 試験キーワード |
|---|---|---|
| 第1条 | 通関業法の目的 | 通関士設置・迅速適正な手続 |
| 第2条 | 通関業務の定義 | 独占業務・輸出入申告・不服申立て |
| 第7条 | 関連業務 | 保税・事前教示・他法令許可 |
| 第22条 | 帳簿・届出・報告 | 3年保存・財務大臣届出・年1回報告 |
【通関士試験対策】過去問チャレンジ!
独学に不安な方へ|短期間で合格を目指すなら通信講座がおすすめ!
通関業法は暗記だけでなく、制度背景や条文の理解も求められます。独学での限界を感じたら、プロの講義で効率よく学べる通信講座の活用を検討しましょう。
✅【アガルートアカデミー】
-
通関士・行政書士・社労士など国家資格に強い!
-
初学者にもやさしい動画講義+過去問対策
-
合格者の声も多数掲載!
関連記事のおすすめ
📘課税価格決定の原則の例外とは?【通関士試験対策シリーズ】
📘【通関士試験対策】特殊関税とは?便益関税・相殺関税・不当廉売関税等を解説
📘【2025年最新版】通関士試験に独学で一発合格おすすめできるテキスト8選